こんにちは
臨床検査技師のとっとろです
梅雨も明けて、連日晴天&高気温が続いてへたっています
はい。今日は大学生だった時のことを書いていきます!
授業ばかり?
医療系の学校を卒業していると、よく他学部の人たちに聞かれたのが
「朝から晩まで4年間授業びっしり入ってるの?」とか
「実習だらけでレポートに追われてるの?」
などよく聞かれていました。
正直、皆さんがイメージしているよりは授業は少ないかと思います。
1年生の時は週4でバイトしていましたし、バイトのない時はサークル活動も参加していました。
今考えるとよく倒れなかったなーと思う時もありますが、当時は全く苦ではなかったです。
1年生
1年生の前期は、英語や第二言語の授業だったり
基礎科目(生物学や生理学・解剖学など)を授業で教わります。
科目によっては高校生の時の復習+α程度の内容でした。
ちなみに体育とかもあって、他の学科の友達とかもできていました。
後期になると血液学や免疫学などの専門科目がちょこっと出てきて少しずつ難易度が上がります。
しかし、レポートなどはほとんど提出を求められることはなく、授業も教科書に沿って行われたり
先生が配布する資料をもとに授業が行われました。
2年生
2年生になるとほとんどが専門科目の授業になります。
1年生の時に習った専門科目は
血液検査学や免疫検査学など、より検査の基礎などを学ぶ科目が増えていきます。
検査学の座学が終わると、検査学実習となり実習がメインとなります。
実習では現在臨床で行われている検査の原理や基礎を用手法(人が手で実際に検査を行う)で学び、レポート提出を指定された期日までに提出します。
レポートはパソコンを使って作成していいかもくと、必ずノートに書いて提出を求められる場合があり、
提出方法は担当の先生によってまちまちでした。
3年生
3年生になるとメインは実習と国家試験対策の授業が開始されます。
当たり前ですが、国家試験に合格しないと就職先の内定は取り消しになってしまいます。
私のいた大学は二年生の後期から三年生の前期がもっとも実習と授業がおおく、レポートも大量に書いていました。
また学校によっては研究室に配属になり、基礎研究や専門知識を広げていくのも、この辺りになります。
授業だけでも覚えることたくさんあったのに、研究室でも課題が出され、てんやわんやします。
実習も予定通り結果が出れば、まとめるだけで済みますが、予定外の結果になると何故この結果になったのかを推論してなくてはならなく、余計に手間取っていました。(この頃は辛かった‥)
病院実習も大学では3年生の時にいくことが多く、学校によっては実習に行くだけの知識があるかを問う試験もあります。
試験を通過しないと病院実習には行けない=国家試験は翌年に持ち越しになります。
4年生
4年生になると、基礎的な授業はほとんどなくなり実習も激減します。
しかし、国家試験対策の授業が増えていき、ついていくのも大変ですが、知識として吸収できるので非常に楽しいです。
就職活動も4年生に行います。
授業の多さは段違い
授業の数だけで言うと普通の大学生活を送るには段違いに多いです。
卒業要件が120単位ぐらい?あれば卒業できるのですが、私は160単位ほど取得して卒業しました。
単位換算されない授業も多々あるので実際には180単位は超えているのかなと思います。
授業のコマ数管理も自由にすることもできますが、基本的に
授業は決まった場所に割り振られているので、
「水曜日は休みに日にしよう!」などはできません。
でも楽しい
ここまで学生生活を苦行的な内容で書いてきましたが、
個人的には勉強したくて臨床検査技師養成課程に進学したので、非常に楽しい日々でした。
知らないことを学び、教科書で学んだことを実際に手を動かしか目の前で再現できる楽しさ
研究室の同期や、同じ目標を目指す仲間とともに勉強する時間
今思い出しても、楽しいことの方が多かったです。
戻れるならばもう一度学生生活を過ごしてみたいと思います。
もし進学を悩んでいる方がいれば参考になれば幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
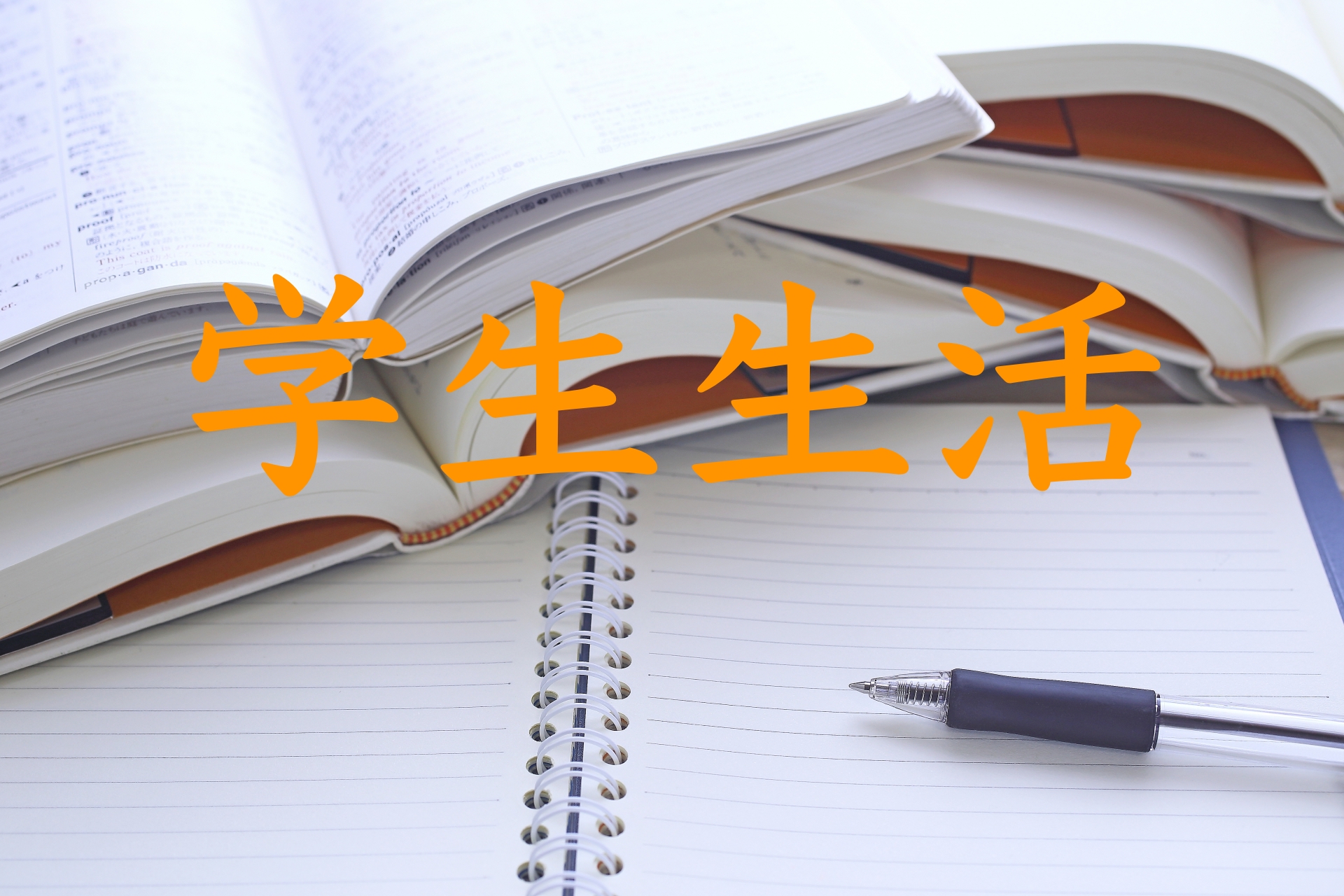

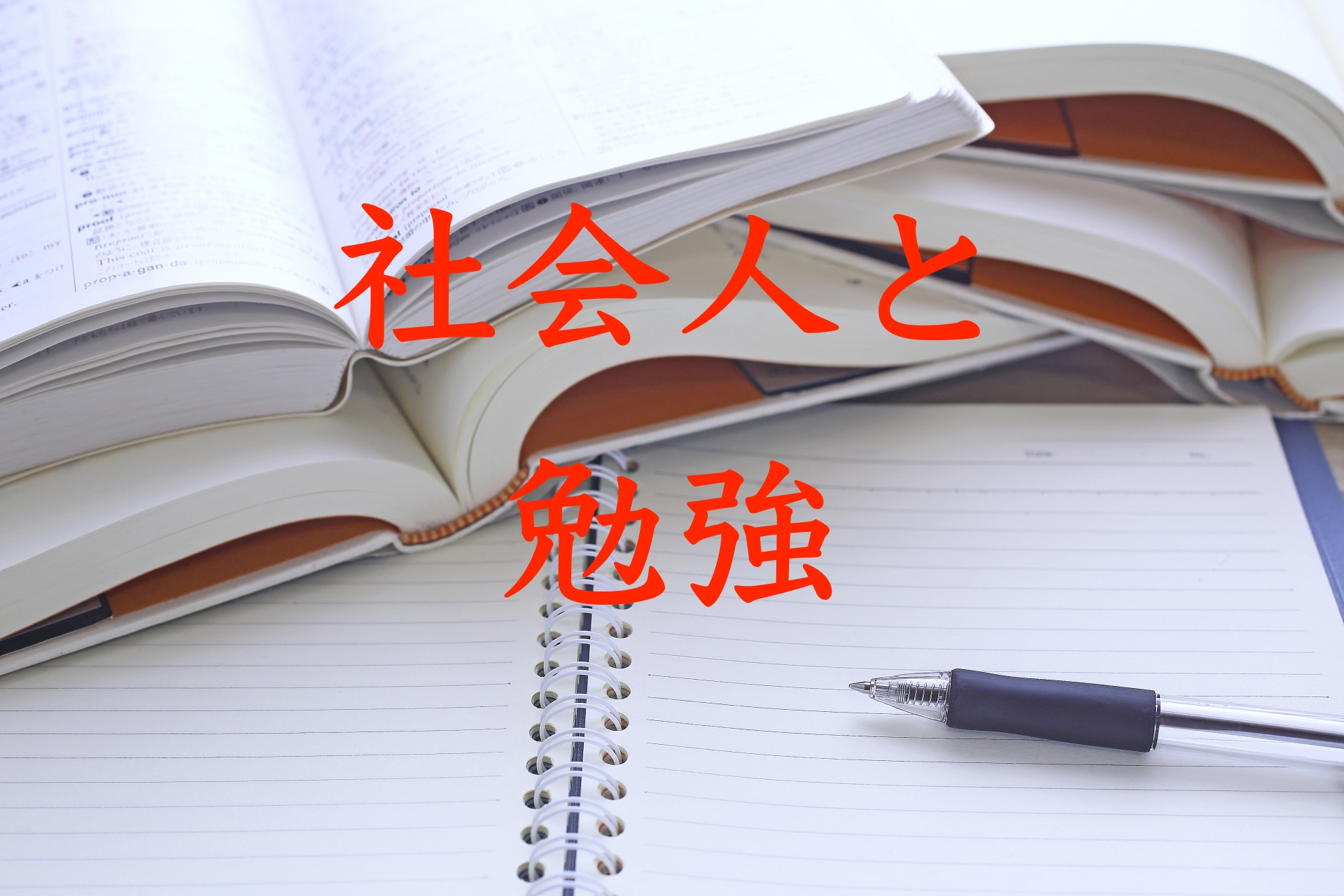
コメント